私がミニマリストを目指した2015年当時に読んだ本を再読してのレビュー記事。
3回目となる今回は、漫画家 中崎タツヤさんの著書「もたない男」を紹介します。
もたない男 中崎タツヤ 著
著者の中崎タツヤさんは漫画家です。
この本を読んでいた当時、ビッグコミックスピリッツも毎週欠かさず読んでいて、「じみへん」の作者さんなんだなということがすぐにわかりました。(現在は漫画雑誌をチェックする習慣がなくなってしまいました。スピリッツで代表的な漫画は「闇金ウシジマくん」など)
「じみへん」は4コマ(15コマ?)漫画で、シンプルな絵柄とシュールな展開が特徴。
3年前は「持たない男」の文庫版を購入していたのですが、いったん手放し、再度新書版を書い直しました。
第1章 なぜもたないのか?
著者の中崎タツヤさんは、天然のミニマリストで、持たない生活を目指してこのようになったのではないと思います。
私の持論ですが、ミニマリストには、ミニマリストの良さに目覚めてモノを減らした“普通のミニマリスト”と、そのようなライフスタイルを意識せず、自然とモノがない“天然ミニマリスト”の2つに別れると思っています。私は前者です。
中崎さんの仕事場にはパソコンもなく、携帯電話もほとんど使っていないようです。
パソコンをインターネットに繋げていると、余計なことに目が行ってしまって仕事に集中できないそう。
漫画を書くのは厳選した道具で、手書きで書かれています。漫画の絵柄的にも、デジタルよりアナログの方が合っていそうですね。
中崎さんが普通のミニマリストと違って面白いなと思ったことは、無駄だと思うモノ(部品?)は徹底的に削ぎ落とすといったところ。
たとえば、
- 椅子の背もたれを切り落とした
- ボールペンのキャップに付いているクリップを削った
- ボールペンのインクが無くなってきたら短く切り落とす
などです。
普通モノを減らしたい人は「捨てる/持ち続ける」の2択になると思うのですが、いい意味で斜め上を行ってます。
カスタマイズしてまで極限にモノを減らす姿勢は、見習えるところは見習いたいと思います。
あと、「バイクのフェンダー(泥除け)を外したら雨の日に大変だった」とか「車のヘッドレストを外したら車検に通らなかった」などの失敗談も載せられています。
総じて、モノが少ない方が集中できると考えているため、持たないようにしているそうです。
第2章 なぜ捨てたいのか?
なぜ捨てたいのか?
中崎さんにとってモノを捨てることは主義でも美学でもなく、ただ無駄が嫌いでスッキリしたいだけとのこと。
使い切らなくても、全然ものを捨てられます。
私の判断基準は、いるかいらないかだけです。
なんともストイックですね。(本人はあまり意識してなさそうですが)
中でも印象的だったのが、読み終わった本のページを破って捨てる話。
これは上で紹介したボールペンを切り落としたり、椅子の背もたれを切り落とす話に似ていますね。
読んだページを捨てて本がコンパクトになる様子も、イラスト付きで紹介されています(笑)
あと、後の方の項目で、本棚に入れた時にそれぞれの本の高さが揃わないから、彫刻刀を使って高さを揃えたというのもありました。
さすがに中崎さんも出版に関わる仕事をしていることから、本を破ったり捨てるのには抵抗があり、図書館を利用することにされたようです。
妻を口説く
本書で紹介されている中崎さんの部屋は漫画を描くための仕事部屋です。
自宅は別にあり、奥様と二人暮らしをされているようで、自宅の様子は特に紹介されていません。
職場は自分の好きなようにできるけど、自宅は奥様が決定権を握っているようで、「不要だな」と思うものもたくさんあるようです。
ソファを捨てるために、奥様を説得した話が載っています。
私も同じように、多すぎるモノや、モノを増やそうとするのをやめるよう頑張って奥さんに説得している立場です(笑)
「これだからミニマリスト()は…」と言われて、なかなか思い通りに行かないことばかりですが…
便利すぎてはつまらない
ミニマリストの間では定番となっているキャッシュレス生活。
中崎さんは、Suicaを使っていたけど結局現金を持っていれば済むわけだからSuicaは捨てて、でもまた買い直してのせめぎ合いが続いているようです。
キャッシュレス生活をしてても、結局現金って必要になるんですよね…
結局現金が必要になるパターンが少しでもあるのであれば、現金オンリーに寄せてしまおうという考えは私にもあったし、難しいところです。
お遍路で捨てる
何と、著者の中崎さんは私と同じ愛媛県の出身でした。(本書を読むまで知りませんでした)
四国には「四国八十八ヶ所巡り」というお寺を巡る行事があって、札所であるお寺の近くでは、お遍路さんをよく見かけます。
中崎さんは、奥様と二人で八十八ヶ所を歩いて巡る歩き遍路に挑戦されたようです。
本州在住の方にはあまり馴染みがないかもしれませんが、四国一周って結構な距離があります。
全行程で1,200kmほどあり、40日間くらいかけて巡ったと書かれています。
一日約40kmを毎日歩く疲労感は想像がつかないです。歩きながら、とにかく荷物を軽くするために不要なものを捨て続けて、パンツも最終的に2枚だけにしたようです。
この経験から、普段も「パンツは2枚だけでやっていける」との結論になったみたいですね。
個人的に、この章で書かれている、奥様と歩いて四国八十八ヶ所を巡礼した話が一番グッときました。
第3章 持たない生活
ファッション
この章では、天然ミニマリスト中崎さんのファッションについても紹介されています。
基本的に、ミニマリスト間で定番の「私服の制服化」の概念で白いポロシャツを3枚で着まわしたり、ナイキのアンダーウェアとシャツを3着でローテーションしているようです。
服は消耗品
これは、ミニマリスト3年目になって私がたどり着いた回答です。
初期は、わりとそこそこのブランドで制服化するシャツやパンツを揃えていました。(ビューティ&ユースやナノユニバース、N.HOOLYWOODなど)
しかし、これらの服って「高いから丈夫で長持ちする」わけではなく、耐久性的にはユニクロと同等かそれ以下です。
もちろん、デザインやシルエットはいいのでその部分にお金を払う価値は十分にあると思います。
最近は、ユニクロなどのファストファッションもデザインがシンプルで洗練されてきているので、現在は「服はユニクロ、時計や財布などの小物はお金をかけて一番好きなものを買う」というルールに徹しています。
中崎さんは、他人のファッションを見ても不要なモノが付いているのが気になるらしく、キャバ嬢の盛り髪や、ウェーブのかかったヘアスタイルなどが苦手なようです(笑)
あと、自分が着るポロシャツやTシャツにワッペンなどがついている気になるらしく、不要なワッペンなどがあったら剥がすそう。
ここでも中崎さんらしさが出ていますね。
食事
理想はNASAの宇宙食とのこと。チューブでお腹が満たされて栄養が補給できるならそれで良いという考えらしいです。
中崎さんは、楽しみのための食事と生きるための食事は別と考えており、仕事中の栄養補給だったら時間がかからない方が良いといった考え方です。
なるほど…
私はわりと、3食きっちり食べたいものを食べる派なので、食のミニマリズムについては共感できる部分と共感できない部分があります。
周りの人と楽しみのための食事を大事にできればそれでいいのかなと思います。
お金はものである
本書でかなりツボにハマった項目。
みんな、お金がほしいわけですが、なぜかというとものがほしいからだったりする。
(中略)
何らかのものがほしいわけで、ほしいものと交換できるお金がほしいわけです。
(中略)
お金自体、貨幣自体をほしい人は、古銭マニアの人たちくらいでしょう。
お金が行き着く先にはものがあって、だからこそ人間はお金がほしいと思うんです。
今でこそ、お金をもの以外にサービスと引き換える考え方も一般化してきましたが、基本的には「ものと交換できるから」お金がほしいわけですよね。
ものを抽象化したのがお金であって、お金には全てのものの要素が入っている。
独自の感覚で書かれたお金についての考えは目から鱗でした。
第4章 もたない人生
この章では、中崎さんの仕事や家族、人生について書かれています。
高校を卒業して、室内外装飾の会社にデザイナーとして入社。4ヶ月で退社し、オーストラリアへ移住することに決めたそうです。
ワーキングホリデーなどもなかった時代にその決断は凄いなと思います。色々あって10日間で帰国されたようです。それから色々あって漫画家に…
若い時って色々挑戦したくなるし、実際に行動に移せただけでも十分な経験だったのではないかと私は思います。
そのほか、父親のこと、母親のこと、奥様のことなどがこの章では紹介されています。
ミニマリスト本で家族のことに触れている本は少なめだと思うので、ぜひ本書でご覧いただければと思います。
第5章 捨てられないもの
捨てられなかったけど、結局は捨てたもののお話となっています。
- 漫画の原稿
- アルトサックス
など
「自分で描いた漫画の原稿を捨てるのは抵抗があるのでは?」と思いました。デジタルでスキャンするのも面倒になって、結局全部燃やしてしまったようです。(おそらく出版社には残っているのだと思われます)
未収録作品は、結局自分が気に入ってないものなので、捨ててしまっても問題はないと書かれていました。
何ともストイックですね。
アルトサックスは、「吹けたらいいな」で購入したけど、しばらく手元に残っていたようです。
私も楽器をやっていた身としてよくわかります。「いつかは演奏できるだろう」「できなかった自分を認めたくない」趣味の道具はそういった考えで、手放すのを先送りにしてしまいがちです。
結局は質屋で5万円くらいになったようです。
まとめ
こちらの「もたない男」は、既存のミニマリスト本とは全く異なるアプローチで書かれています。(そもそも書かれた当時ミニマリストという言葉はなかったはず)
著者の中崎さんは、とにかくシンプルが好き。その結果このようなライフスタイルになったのだと思われます。
私の場合は、自制していかないと結構モノを増やしてしまいがちなので、このような天然のミニマリスト的な生き方ができることは羨ましいです。
「ミニマリストって冷たい人が多いのでは?」といったイメージもありますが、本書では中崎さんの人間味も凄く溢れていて、家族を大切にされているなと思いました。
物質的なモノに対しての考えは冷徹でもいいけど、周りの人との関わりは大事にしていきたいものです。
ミニマリストとして、新しい考え方を持てる一冊でした。
それでは、よいシンプルライフをお送りください^^

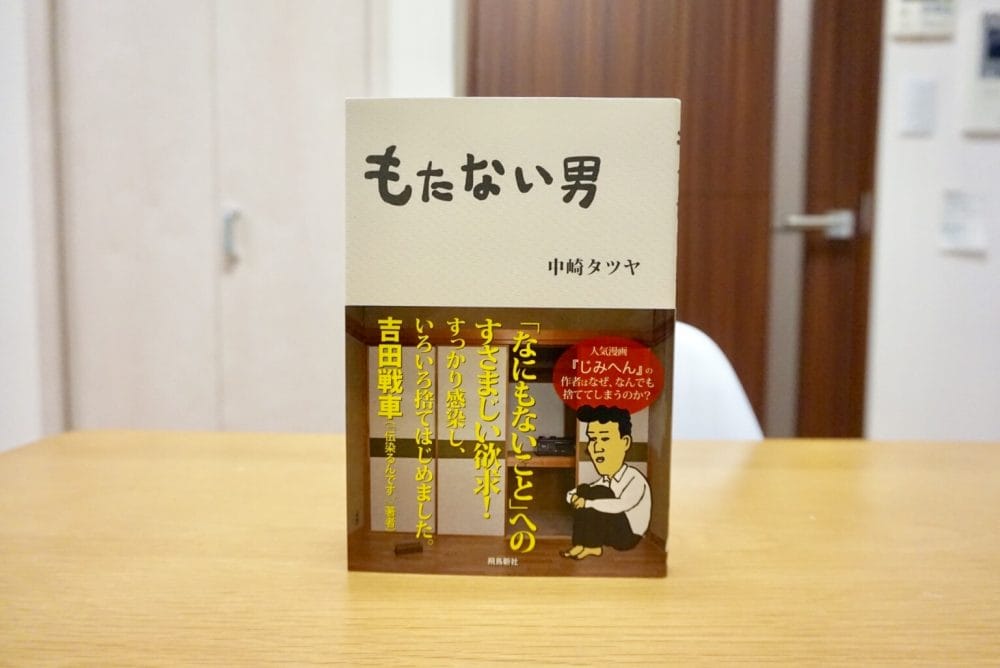




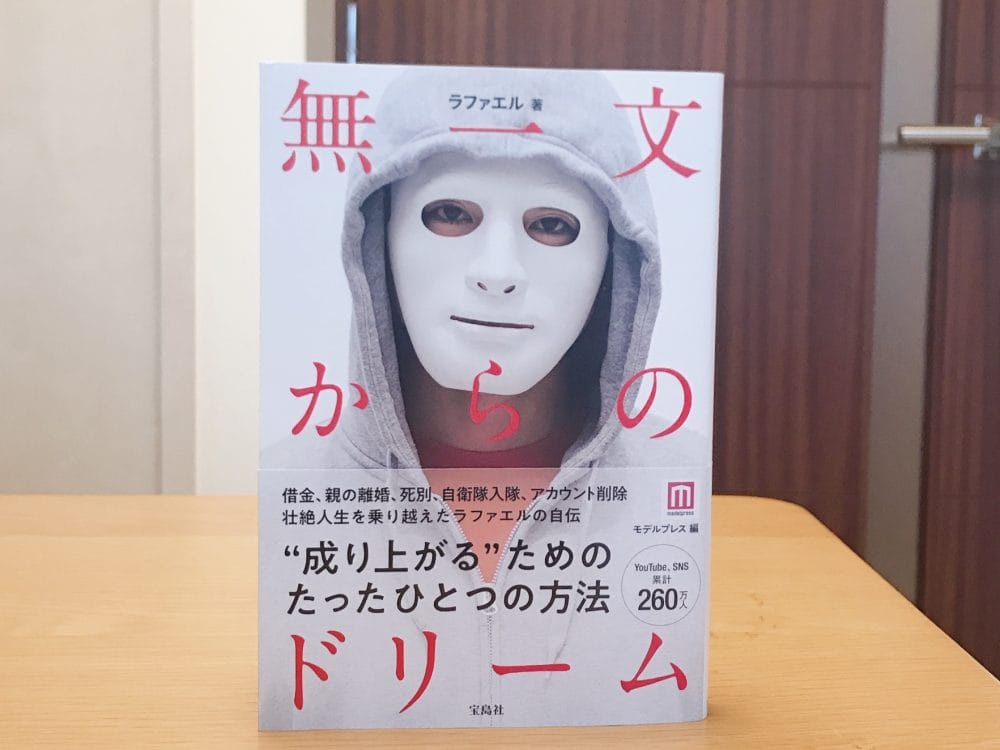
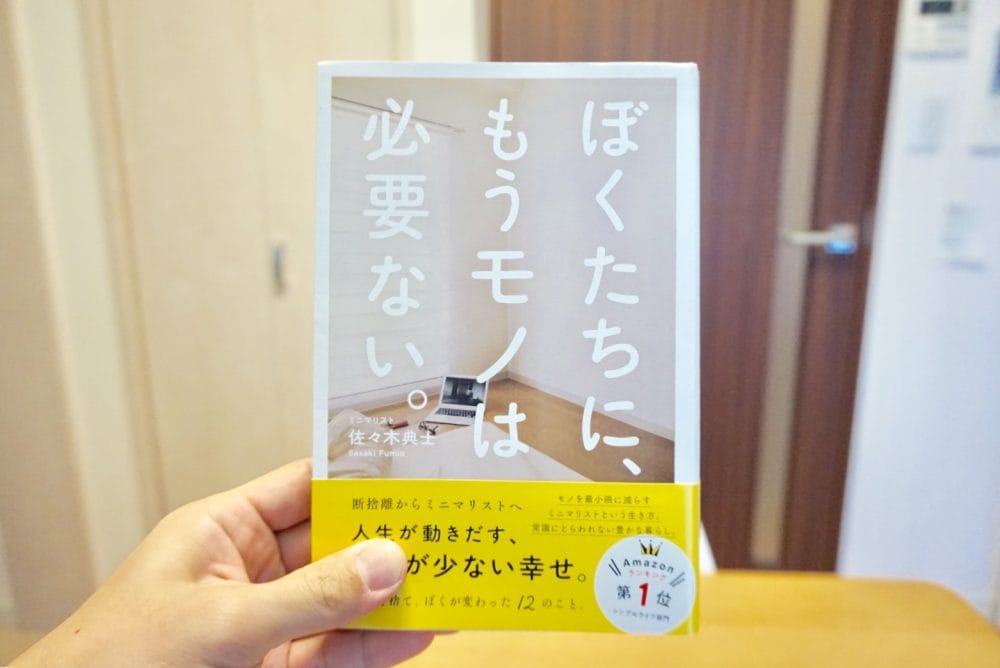
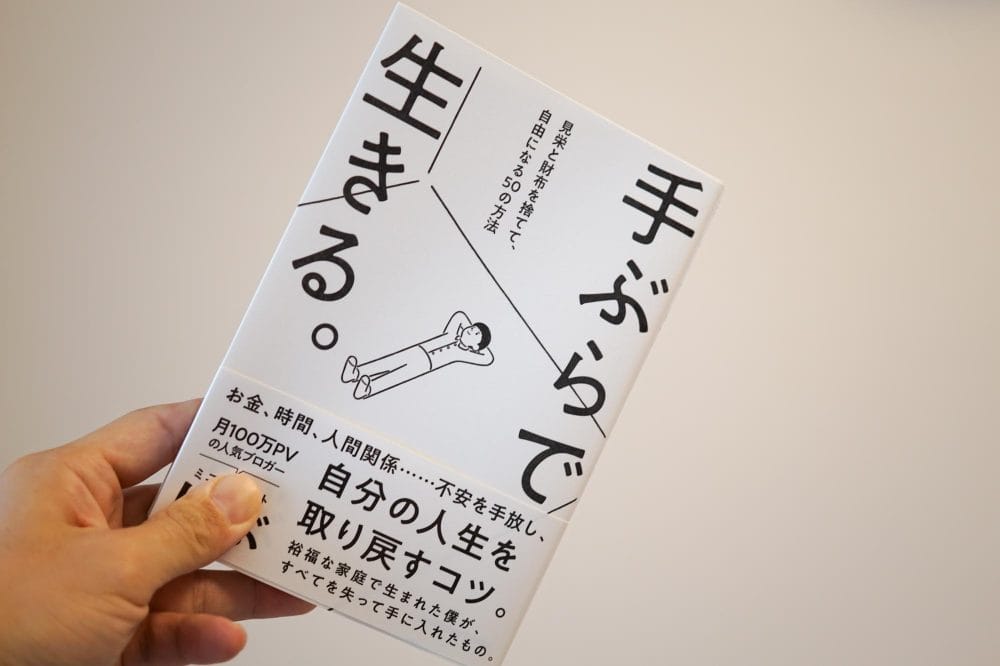
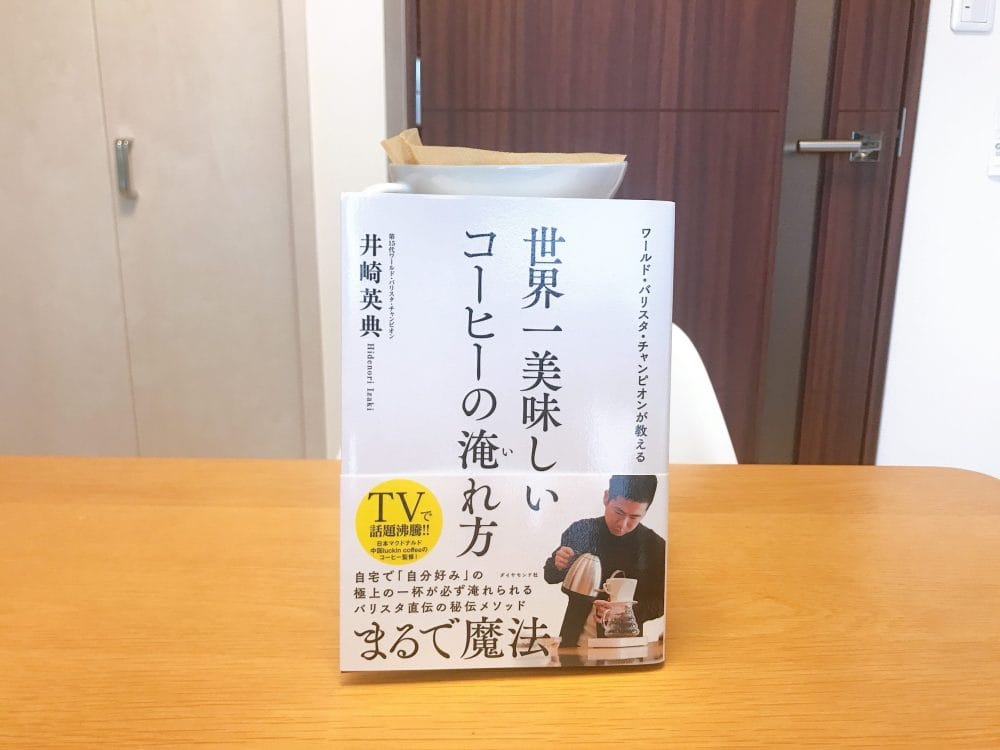
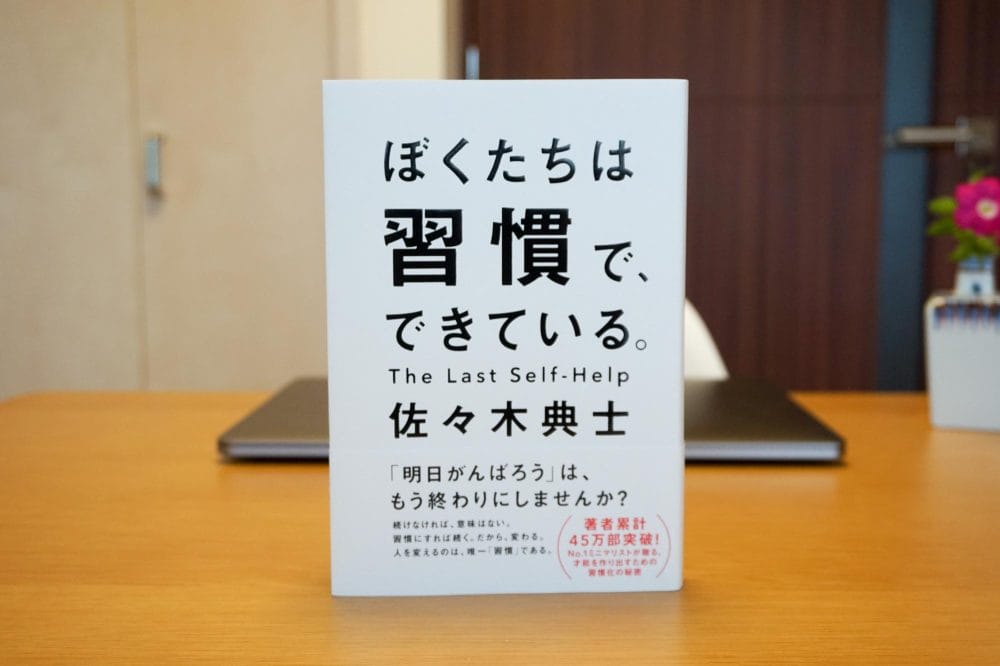
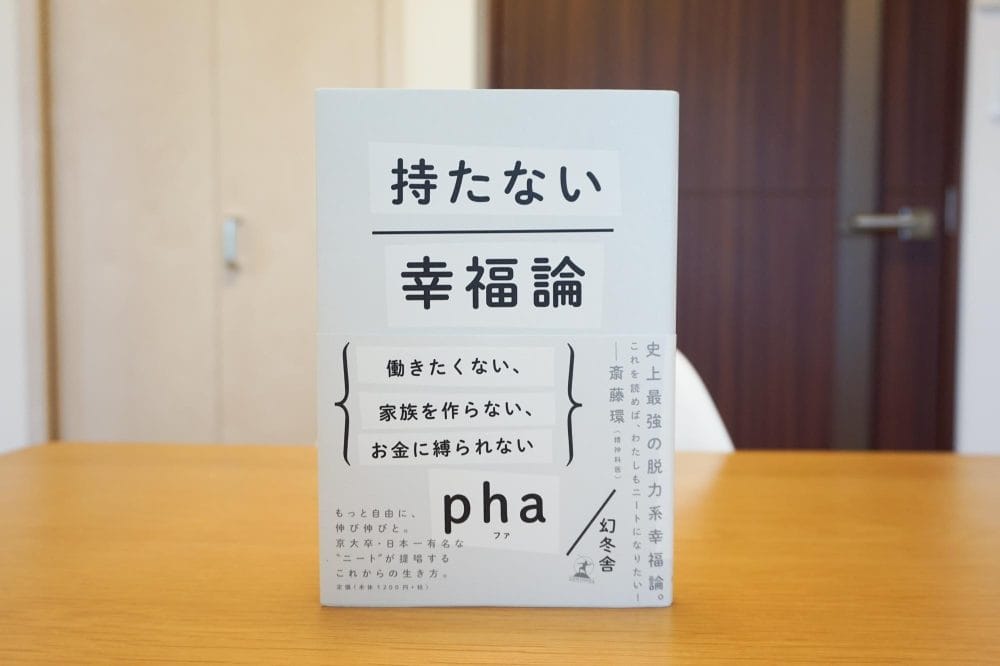
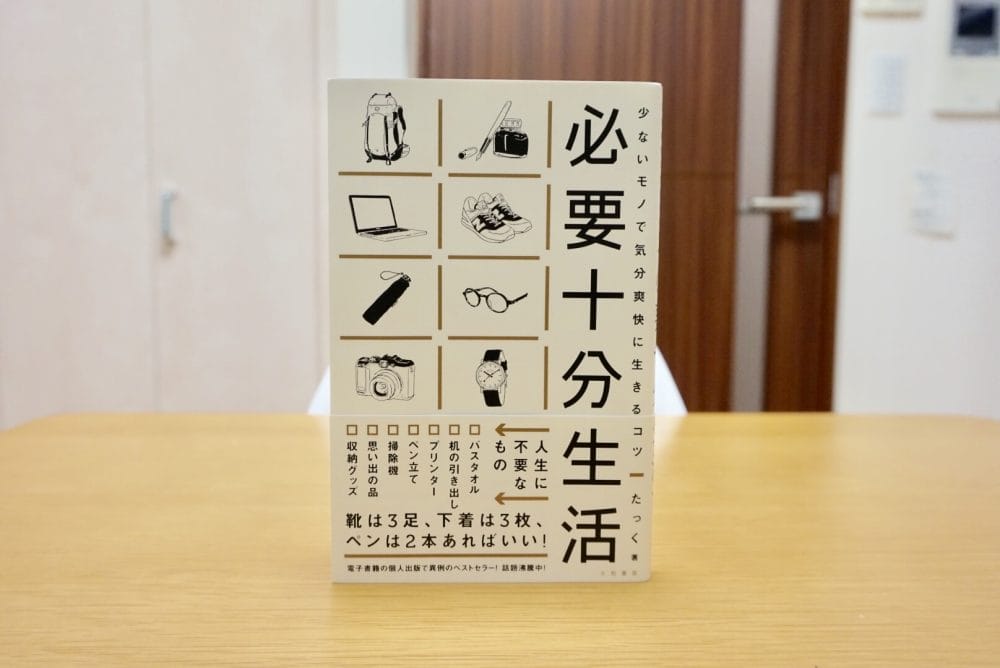



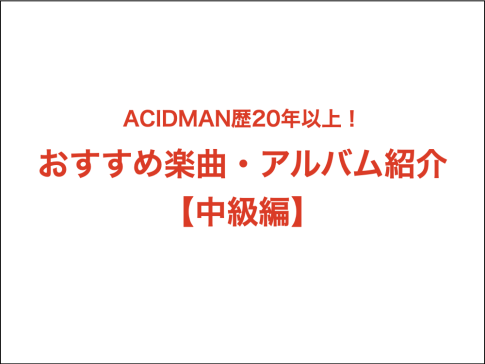



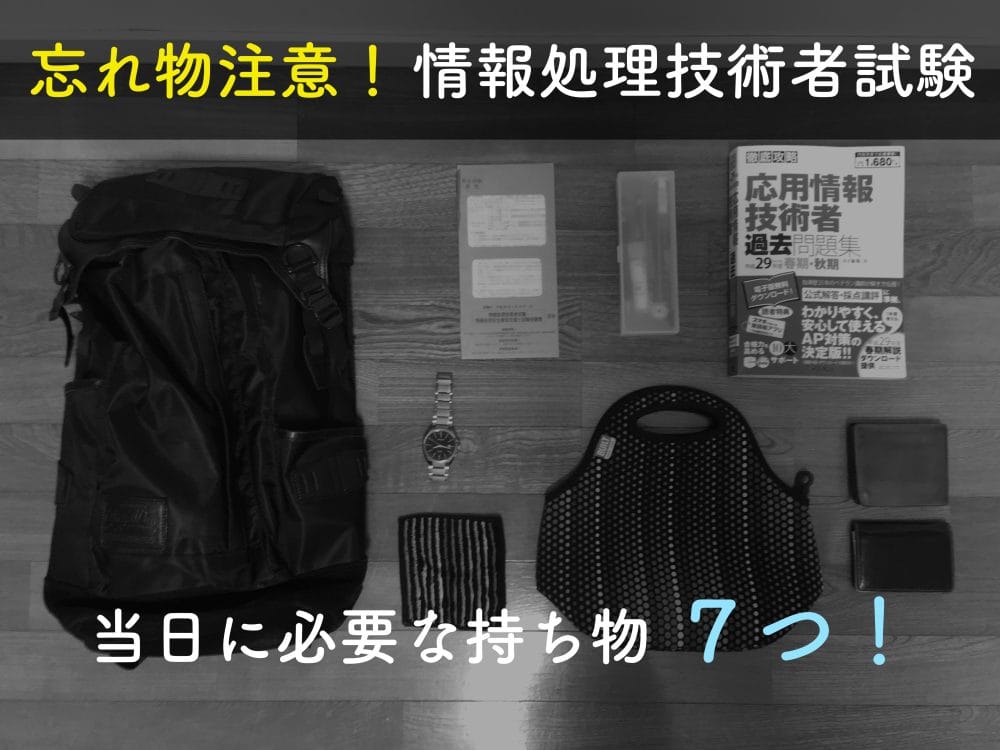







コメントを残す