2018年5月27日、Cisco認定試験ICND2に合格して、CCNA(Routing&Switching)取得となりました。
今回は、CCENT(ICND1)合格後からの道のりと、試験対策について紹介したいと思います。
ICND2初受験の結果
820点が合格点である中、832点で合格となかなかの辛勝。
当日のツイートにもあるように、開始数問で「今受けているのは本当にICND2か?」と目を疑いました。
どのような内容だったかについては後ほどの項目で紹介します。
正直、これで不合格だとしたら「何を使って試験対策をしたらいいのかちょっと見当がつかないな」と思いながら試験終了のボタンをクリックしました。
全体的なCCNA取得の勉強時間
- ICND1合格まで ・・・ 5ヶ月(4ヶ月ダラダラ。1ヶ月みっちり)
- ICND1合格からICND2合格まで ・・・ 1ヶ月半みっちり
ICND1合格時の記事は、こちらもご覧ください。
Cisco試験に限らず、この手の資格試験は“何も分からない0の状態を1にする”段階が一番難しいと思います。
例えば、同じIT資格の情報処理試験にしても、「何もない状態から基本情報技術者を取得する」と「基本情報技術者を取得後に応用情報技術者を取得する」では、前者の方が断然難しいです。
そのため、ICND1に合格していればCisco機器の基礎的な知識は備わっているため、ICND2を合格ラインに持っていくことは最初のICND1の知識を身につけるよりは少ない時間で済むと考えてます。(それでもICND2はなかなかの難易度)
CCNA全体の難易度は?
体感的に、ICND1とICND2を総括したCCNAの難易度について紹介します。
今まで取得した(受験した)他のIT試験と比べると、
ITパスポート > LPIC1 >> CCNA > 基本情報 > 応用情報 >> ネットワークスペシャリスト
ぐらいの感覚です。(「>」の多さはより難しいことを表します)
基本情報などの国家試験に比べて暗記が必要になってくる部分が多いのが、難しいというか面倒です。(知らないと問題を解けない)
それでも、基本情報のように数学的な計算やアルゴリズムなどの問題はないので、暗記さえできれば文系でも十分取得できます。
基数計算とサブネット計算、帯域幅や速度の計算ができれば十分です。
どのような問題が出題されたか?
問題の転載や詳細な内容を公開することは禁止されているためアバウトな記載となりますが、「黒本問題集やPing-tとは少しかけ離れた問題が多かったかな」という印象です。
シミュレーション問題は、以外にもPing-tなどの問題よりも簡単で、SDNやQoSについて聞いたこともない用語を交えた問題がたくさん出てきました。
知らないものはいくら考えてもわからないので、消去法で答えを選択して先に進むしかありません。
冒頭にも書いたとおり、CCNPやCCDAなどの別分野の試験を間違って受けているのではと思うくらい想定外な問題が続いたので精神を削られました。
Ping-tの合格体験記を見ても、皆同じようなことで苦労されているようなので一度は目を通すことをお勧めします。
一番のネック”Cisco語”について
前回記事にも書いたとおり、Cisco認定試験には英語を翻訳サイトでそのまま日本語に翻訳したような不自然な日本語での出題がよく見られます。
こちらのサイトに具体的に書かれていました。
- 選択肢の文中に、主語となる「は」が2つ入っており、何を指しているのか判別がつかない。
- 「〜コマンドが設定されていない」などと、主旨は読み取れるが一瞬悩んでしまうような言い回しが出て来る。
- コマンドに付加するオプションのことを「キーワード」というように別の単語を使ったり、「ネットワークステートメント」などとと問題集であまり見ない日本語訳が使われる。
- 選択肢全てを見てもぴったりと来る選択肢がないときがあるので要注意。問題文、あるいは選択肢の日本語が正しい表現ではない可能性があるので、「これは絶対にない。」という選択肢を排除して消去法で回答を導かなければならない時がある。
本当にそのとおりです。
こういった要素もあるので、合格についてはある程度運の要素も絡んでくるなとICND1の時以上に思いました。
Cisco語の対策としては、Ping-tよりもやや高額な問題集サイトクラムメディアを利用するか、英語が得意な方であれば英語で受験することをお勧めします。
有効な勉強方法について
こちらも前回のICND1の時と同様に、Ping-t問題集と黒本問題集の繰り返し学習をおすすめします。
また、ICND1の時に当ブログで紹介したサイトにて、ICND2の範囲も全てカバーすることができます。
ICND1とICND2で特に違った対策を取る必要はありません。ただひたすらに試験範囲を勉強しましょう。
個人的に、問題集をひたすら解く”アウトプット学習”と、教科書やサイトを見てノートにまとめる”インプット学習”を6:4くらいでするのがおすすめです。
実機での検証は効果的?
効果的か効果的でないかと言われると“効果的”であることは間違いありません。しかし、実機の調達や収納スペースなどを考えると誰もが実機を用意できるわけではないと思います。
個人的に、CCNAレベルであれば“実機を全く触ったことがなくても”普通に合格できると思います。
しかし、理解の深さや速さ、実務での有効性を考えると、実機を触っておくことは本当に意味のある経験となります。
ただ手っ取り早く資格が必要というだけであれば、実機での練習はなしでも問題ありません。今後、ネットワークエンジニアとしてバリバリやっていきたい方は、実機に投資して理解を深めることをお勧めします。
もしかしたら会社が検証機器を貸し出してくれるかもしれないので、周りに相談することも大切ですね。
CCNAは一括受験の方がよかったかもしれない

当ブログでは、不合格時のリスクを分散するためにICND1とICND2を分割で取得することをおすすめして、私も分割で取得しました。
しかし、ICND2の難易度(というか意味不明さ)を考えると、CCNAを一発で受験した方がおかしな問題が減る可能性が高いのではと今は思います。(問題数は同じであるため、細部まで問われる部分が少なくなる)
さすがに一発4万円の受験料はリスクが高くて簡単に受けられるものではないですが、両方の範囲を細部まで理解していれば一発で合格できる可能性は高いです。
分割受験がおすすめな場合と一括受験がおすすめな場合について紹介します。
分割受験はこのような場合に
- 場合によってはCCENT(ICND1)の取得だけで良い
- 会社から分割で受験するように指定されている
- とにかく細部まで理解して、今後の糧にしたい
分割受験のメリットは、1回の受験料が約2万円であるため、落ちた場合のリスクを分散できることです。
最悪、CCENT(ICND1)だけ取得しておいて、3年以内にICND2を受験でも問題ありません。
CCENTの合格だけでも、1つの資格として扱われます。(実用性はさておき)
一括受験はこのような場合に
- 最短・最速でCCNAを取得したい
- 普段からCisco機器を触っているから自信がある
- 短期集中で勉強できる環境にある
- 資格はサクッと取得してあとは実戦で鍛える
短期集中で両方の試験範囲をマスターできれば、一括受験のほうが楽です。
しかし、慎重に行きたい方は無理せず分割受験にしましょう。
IT,Cisco未経験者は?
未経験で転職のためにCCNAを取得する場合は、無理せず分割受験を選びましょう。
範囲が広いため、まずはICND1分野をしっかり覚えて合格後、ICND2に取り掛かるのが良いです。
CCNAが必ずしも転職に有利な資格とは言えませんが、若ければ若いほど、色々なことに挑戦する上で有利になります。勉強に割ける時間があって興味がある場合は、是非とも挑戦しましょう。
まとめ:「運」の要素も大きいICND2
ICND2についてはICND1と違い、「対策していたものと全然違う」といった感想でした。
Cisco語や聞いたこともない用語の問題は、本当に運としか言いようがありません。
その中でできることとして、
- わかる問題は絶対に落とさない
- わかる問題をできるだけ増やす
- 時間切れにならない
ことです。
特に最後の「時間切れにならない」ことはとても大切です。90分の制限時間は結構余裕があるようで、シミュレーション問題の読み解きと解答を考えると余裕がありません。
1問2分以内に回答が必要です。
わからない問題はわからないと割り切って、「選択肢の中から明らかに違うものは外す > 残った選択肢からより近そうなものを選択する」といった消去法での回答が必要です。問題の中には配点がなかったり配点が低かったりするものも含まれるため、知らない問題に精神を削られないようにしましょう。
じっくりやれば必ず合格できます!
それでは、よいシンプルライフをお送りください^^















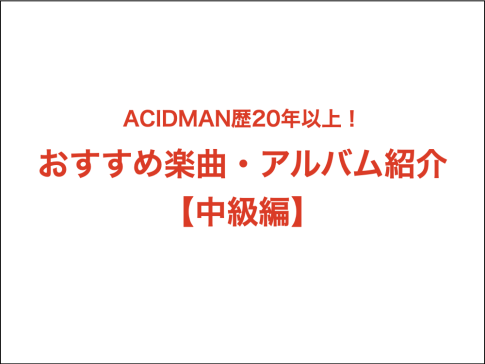




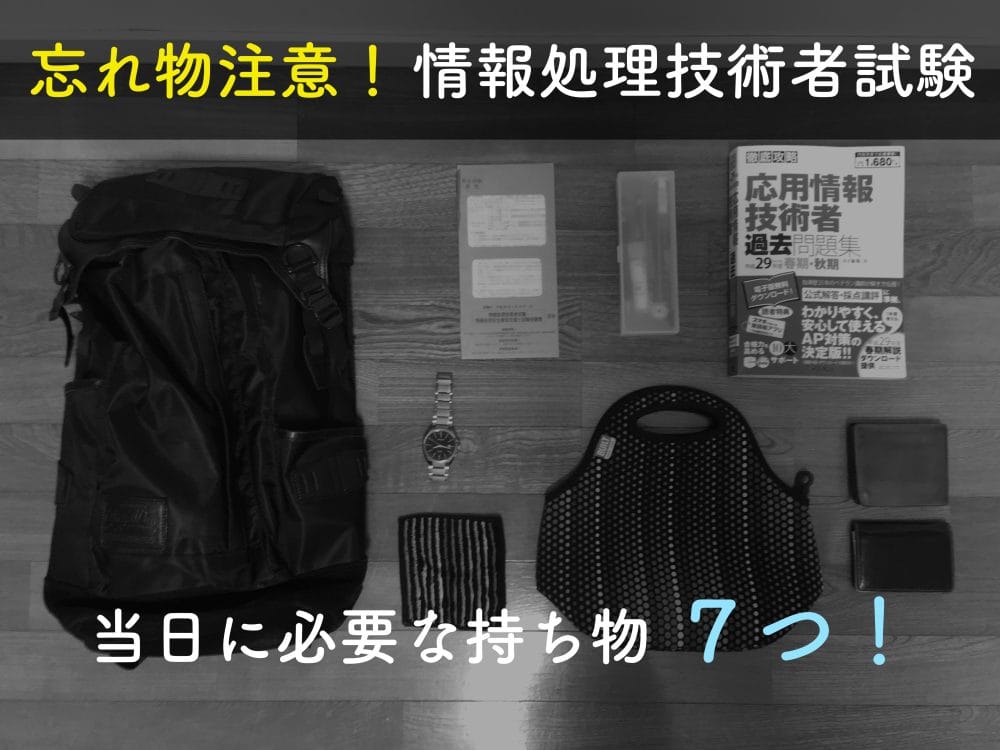






コメントを残す